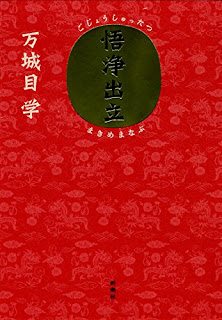鎌倉前期の高名な歌人・藤原定家はある日、父・俊成から三種の御題を解けば「古今伝授」を授けると言われるが、数ヶ月後、俊成は何者かに誘拐される。その目的は一体どこに?鍵を握るのは御題の暗号解読。美貌で毒舌の僧侶・長覚と、紀貫之と同じ紀氏の血を引く少年・潮丸と協力して、父・俊成の救出に奔走する定家。伝統的な和歌の修辞法と謎合わせをモチーフに公家社会の権力の闇に迫る、平安鎌倉ミステリシリーズ。
2015年4月19日日曜日
幻の神器
鎌倉前期の高名な歌人・藤原定家はある日、父・俊成から三種の御題を解けば「古今伝授」を授けると言われるが、数ヶ月後、俊成は何者かに誘拐される。その目的は一体どこに?鍵を握るのは御題の暗号解読。美貌で毒舌の僧侶・長覚と、紀貫之と同じ紀氏の血を引く少年・潮丸と協力して、父・俊成の救出に奔走する定家。伝統的な和歌の修辞法と謎合わせをモチーフに公家社会の権力の闇に迫る、平安鎌倉ミステリシリーズ。
2015年4月14日火曜日
失われたミカドの秘紋
「天皇の真実を公表する」そう息巻いていた友人が死んだ。歴史作家・望月真司はその死に疑問を抱き、彼が知った事実を調べるため、支那大陸へ。そこで目にしたのは、キリスト教が中国で流行したことを示す石碑、そして古くからあるイスラム教の寺院。これらが望月の頭の中で結び付けられたとき、ヤマト民族の起源が浮上する!真の古代史を追求する、驚愕の歴史ロマン。
小説といえるかどうかは疑問だが、非常に興味深い考察に「あっぱれ」をあげたい。
2015年3月21日土曜日
華、散りゆけど
時は慶長、大坂の陣。眼下には大地を埋め尽くさんばかりに徳川勢の旗幟がはためく。真田幸村は己の造った出丸に立ち、苛烈な戦場を見据えていた。身に纒うは朱一色の戦装束。狙うは家康の首級ただひとつ。武士に生まれし者の宿命、見事に命の華を咲かせ、武名の芳香を遺そうぞ―たったふたつの戦にすべてを賭けた、稀代の智将の壮烈な生きざまを、濃密かつ流麗な筆致で描ききる戦国歴史巨編。
「花は散りゆけど、その香は残る。されど、われらは死花に非ず!」―父・真田昌幸の言葉を胸に幸村 乾坤一擲の勝負。家康本陣への奇襲は、本書 前半に「布陣図」がありよく理解できた。武士としての「矜持」を貫いた男の最期は美しい。
2015年2月27日金曜日
天平グレートジャーニー
天平五年の遣唐使は苛酷な運命を辿った。朝貢国中最下位扱いされながらも、多くの人士や書物を満載し帰国の途についた四隻の船団。だが嵐に遭い、判官の平群広成率いる第三船は遙か南方の崑崙国へ漂着する。風土病と海賊の襲撃で、百人を越える乗員はほぼ全滅。軟禁されていた広成ら四人だけがふたたび長安へ向かう惨状ぶり。さらには新羅との関係悪化で、北方の渤海国経由での帰国に賭けることに。天平の「外交官」の見たものは?
2015年2月21日土曜日
泣き虫弱虫諸葛孔明 第参部
いよいよ、赤壁場面です。魏の曹操との決戦を前に、呉と同盟を組もとうする劉備軍団。しかし豪族連合の呉は、戦うか降るかでオジキ達の議論が紛糾、カシラの孫権もまとめられない。さらに呉の美しき軍指揮官・周瑜は、変態軍師・孔明に殺意を抱き―。こんなことで赤壁に勝利を刻むことができるのか?いまヤバイ酒見版「三国志」第参部!
2015年2月8日日曜日
真田三代 上・下
戦国の乱世、山間部の弱小勢力であった真田氏を大名にまで育てた三代の男たち。仇敵である武田氏に仕え、旧領を取り戻した幸隆。主君を次々と替え「表裏比興の者」と呼ばれながら徳川の軍勢を二度まで退けた昌幸。そして「真田日本一の兵」幸村―知恵と情報戦で大勢力に伍した、地方の、小さき者の誇りをかけた闘いの物語。
2015年1月23日金曜日
悟浄出立
万城目学著「悟浄出立」を読了。こちらは、短編小説集。
俺はもう、誰かの脇役ではない。深化したマキメワールド、開幕! 砂漠の中、悟浄は隊列の一番後ろを歩いていた。どうして俺はいつも、他の奴らの活躍を横目で見ているだけなんだ? でもある出来事をきっかけに、彼の心がほんの少し動き始める――。
西遊記の「沙悟浄」、三国志の英雄「趙雲」、項羽の愛妾「虞姫」・司馬遷に見向きもされないその娘。秦の始皇帝暗殺を志した荊軻(けいか)と同音異字の京科という名の小役人など中国の古典に現れる脇役たちに焦点を当て、人生の見方まで変えてしまう連作集。
自分の人生を顧みて、「過程こそがいちばん苦し」くて、「そこに最も貴いものが宿ることもある」と悟る沙悟浄。脇役から主役へと哀しくも美しく変身する「虞姫」。などなど---どれもかなり面白かったです。
2015年1月17日土曜日
安禄山
塚本青史著「安禄山」読了。
国際色豊かな唐帝国の全盛期、玄宗皇帝の時代。遊牧民族の小競り合いが絶えない辺境の地で、ソグド人の父と突厥の母をもつロクシャンこと安禄山は謎の日本人・井真成と出会った。商才を磨きながら武人としての出世を重ねた安禄山は、豊かな経済力を背景に、ついに中央で皇帝と楊貴妃の寵臣に上りつめる。しかしそれは、飽くなき権力闘争の幕開けに過ぎなかった―。唐帝国を揺るがした男の生涯を描く、長編中国歴史小説。
本小説は、雑胡(ソグド人と突厥系の混血)の商人としての能力の高さに着目している。また義父に軍人として鍛えられ頭角を現す青年期から、突厥や契丹・渤海国・新羅など非漢民族系6ヶ国語を自在に操った外交手腕、持ち前の陽気さと太っていたにもかかわらず、修敏な舞踊家であったという、個人としての魅力の高さが、安禄山をして一大大出世を果たしたその群像を作り上げている。面白かったです。
2015年1月8日木曜日
峠越え
伊東潤著「峠越え」読了。
信長でも秀吉でもなく、家康こそが天下人たりえた理由とは―。幼き頃、師より凡庸の烙印を押された男は、いかにして戦国の世を生き抜き、のちに天下を覆すことになったのか?本能寺の変、信長死す―。家康の人生最悪の危機は、最大の転機でもあった。大胆不敵の大仕掛け、当代無双の本格歴史長編。
2015年1月5日月曜日
太閤のレガリア
信長はなぜ、それほどまでに秀吉を重用したのか?そこには、それぞれの父・織田信秀と中村弥右衛門の時代、戦闘を一変させた新兵器との意外な繋がりが隠されていた。乱世終息のきっかけとなった安祥城、小豆坂の両合戦と豊臣秀吉の故郷に隠された秘密を新資料から掘り起こし、戦国ヒーローの実像を描く、渾身の歴史大河。
2014年12月20日土曜日
サンクトゥス 上・下
トルコ南部の都市ルインにそびえる城塞―世界最古の巡礼地“シタデル”。ある日、その頂から一人の修道士が奇妙な姿で身を投げた。遺体に刻まれた生々しい傷跡。さらに体内から謎の携帯番号と不可解な暗号が発見される。ルイン警察は、捜査線上に浮かびあがったアメリカ人女性記者リヴとの接触を図るが、時を同じくして、城塞側も、彼女の捕縛と、修道士の遺体奪還を画策していた―世界50カ国で翻訳決定の大型宗教ミステリー。
冬姫
織田信長の二女、冬。その器量の良さ故に、父親に格別に遇され、周囲の女たちの嫉妬に翻弄される。戦国の世では、男は戦を行い、熾烈に覇権を争い、女は武器を持たずに、心の刃を研ぎすまし、苛烈な“女いくさ”を仕掛けあう。その渦中にあって、冬は父への敬慕の念と、名将の夫・蒲生氏郷へのひたむきな愛情を胸に、乱世を生き抜いてゆく。自ら運命を切り開いた女性の数奇な生涯を辿る歴史長編。
2014年11月29日土曜日
ヴァレンヌ逃亡
中野京子著「ヴァレンヌ逃亡」を読む。
[E:book]フランス革命の転換点となった有名な逃亡事件はなぜ失敗したか。
2014年11月18日火曜日
隠された帝 天智天皇暗殺事件
井沢元彦著「隠された帝」を読む。
大化改新の立役者天智天皇は、弟天武天皇によって暗殺された!
天智は暗殺されたと言う仮説を立て、それをいろいろな資料から読み解いていくと言う作業がなされています。さらに、天智天皇と天武天皇は兄弟では無く、しかも、天武天皇が年上であり、暗殺の首謀者が天武天皇だったと言う結論をだし、その裏には、唐と新羅の思惑も絡んでいるという話になっていきます。
日本史最大の謎「壬申の乱」にまつわるこうしたテーマは、やはり興味深いですね。
2014年11月17日月曜日
花冠の志士 久坂玄瑞
復刻版 古川薫著「花冠の志士 久坂玄瑞」を読む。
幕末の乱世、尊王攘夷派志士の中心人物として短い人生を駆け抜けた久坂玄瑞。長州藩医の子として生まれ、黒船来航から間もなく家族を喪ない、攘夷の志に燃えた。松下村塾の双璧として高杉晋作と並び称され、来年の大河ドラマの主人公 「師・吉田松陰先生の妹 文」を妻とした。詩を愛し、武に生き、もののふとして散ったその生涯を描いた決定版。
家族を失い、攘夷の志に燃える玄瑞。
2014年11月9日日曜日
宮城谷昌光著「三国志 第11巻」
宮城谷昌光著「三国志 第11巻」完読。 あと一冊となりました。最終巻は、来年5月らしい。
諸葛亮、五丈原に薨ず。宮城谷三国志、いよいよ佳境へ!
諸葛亮亡き後、魏延と楊儀が対立。蜀は衰退を始める。魏でも皇帝・曹叡が急死し政権運営を巡って混乱が起こる。時代は新たな局面へ。
「麒麟も老いては駑馬にも劣る」三国王朝の創始者の一人、孫権の老害が甚だしい。そうした、孫権の老いとともに呉の没落が始まる。
2014年11月8日土曜日
石原莞爾 マッカーサーが一番怖れた日本人
稀代の軍略家として知られる石原莞爾将軍。
石原莞爾の最晩年ともいえる東京裁判酒田法廷の模様を紹介し、天才・石原莞爾の思想を炙り出したもの。
2014年10月6日月曜日
疾き雲のごとく
『道灌謀殺』 太田道灌
相模国守護扇谷上杉家の家宰太田道灌は、関東の地に安寧をもたらすため、東奔西走の日々を送っていた。やがて、その功績と人望は主人である扇谷上杉定正を凌ぐほどになっていった。道灌のおかげで扇谷家の領土は拡大したが、それを嫉視する内部勢力もあった。彼らの策動により、二人の関係に溝ができ始めた。そんな折、今川家の家督相続をめぐる争いを収めるべく駿河に出向いた道灌は、謎の僧に出会う。
巨大な自我をもてあまし、それにより身を滅ぼした巨人道灌とは何かを問う作品。
幕府の威権も衰えた室町末期、混沌とした関東を統一せんと、上杉定正は東奔西走の活躍をしていた。定正は源平時代の武将に憧れること甚だしく、武芸万般に秀でていたが、特に馬術に関しては名人の域に達していた。その定正の愛馬「龍驤」は稀代の暴れ馬で、定正以外には、乗りこなせる者はいなかった。そんな定正に率いられた扇谷上杉家は、長享の乱において山内上杉家を圧倒し、いよいよその本拠上野国に侵攻することになった。ところが、出陣の直前、肝心の「龍驤」が病に罹った。
室町末期という武士道の端境期(はざかいき)を駆け抜けたドンキホーテ上杉定正を描いた作品。
義母と弟を殺し堀越公方の座に就いた茶々丸は、周囲から恐れられ、孤立していた。そんな茶々丸が、唯一、心を許す相手は修善寺宿菱屋の傾城(遊女)香月だけだった。半ば政務を放り出し、茶々丸は、連日、菱屋に通った。酒と女に耽溺する茶々丸であったが、そんな折、京で政変が起こり、将軍職には、茶々丸を親の仇と憎む義澄が就いた。義澄は茶々丸征伐の御教書を今川氏親と伊勢宗瑞に下した。窮地に陥った茶々丸であったが、公方府の防御には絶対の自信を持っていた。ところが―。
茶々丸という一人の若者の愛と狂気を描いた作品
大磯高麗寺に住む盲目の仏師玄舜が、西相模の実力者大森寄栖庵氏頼に依頼され、岩原城に出向いたのは明応三年(1494)のことであった。氏頼は余命いくばくもないことを覚り、箱根権現近辺に祈願寺を建て、その堂内に神仏混交の理想郷を築こうとしていた。その意を受けた玄舜は、早速、神仏混交像十六体を一心不乱に刻み始めた。しかし―。
自らの信仰に忠実であるがゆえに、悲劇を生んでしまった僧を描いた作品。
永正元年(1504)、叔父の伊勢宗瑞に誘われ、今川氏親は関東に出陣した。宗瑞の支持する扇谷上杉朝良を支援し、山内上杉顕定と戦うためである。宗瑞は氏親を伴い、顕定の進撃路にあたる多摩川南岸に陣を布いた。ところが、味方の足並みは揃わず、二人は窮地に陥る。
稀なる人「氏親」の視線を通して、軍略家宗瑞の一面を描いた作品。
眼前には、首のない父の死骸が転がっていた。住み慣れた寺も焼き払われた。三浦勢は住吉城退去に伴い、父を殺し、父子の寺に火をかけたのだ。その理由もわからず、茫然と佇む妙謙であったが、追っ手を率いる伊勢宗瑞という男に誘われるままに、伊勢勢の陣僧となる。やがて、三浦勢は三浦半島南端新井城に追い込まれるが、新井城は難攻不落であり、伊勢方の攻撃を粘り強く撥ね返していた。考えあぐねた宗瑞が取った次なる策とは―。
戦国黎明期に、自らの信念を貫いた若き僧を描いた作品。
2014年10月5日日曜日
壬生義士伝 上・下
「死にたぐねえから人を斬るのす」新選組で、ただひとり庶民の心を失わなかった吉村貫一郎の非業の生涯を描く浅田次郎版「新選組」。
小雪舞う一月の夜更け、大坂・南部藩蔵屋敷に、満身創痍の侍がたどり着いた。貧しさから南部藩を脱藩し、壬生浪と呼ばれた新選組に入隊した吉村貫一郎であった。“人斬り貫一”と恐れられ、妻子への仕送りのため守銭奴と蔑まれても、飢えた者には握り飯を施す男。元新選組隊士や教え子が語る非業の隊士の生涯。浅田文学の金字塔。
子母澤寛の『新選組物語』「隊士絶命記」が元となっている。何人もの語り手により、その人物像を明らかにしてゆくという技法が良かったです。それにより、吉村貫一郎だけでなく、近藤・土方・斎藤といった多くの隊士の浅田次郎観が表現されていきます。
2014年9月14日日曜日
黎明に起つ
伊東潤著「黎明に起つ」を読む。
京都を主戦場に、11年間も繰り広げられた権力闘争・応仁の乱。それによって荒廃した都の姿に絶望し、挫折から立ち直り、関東の地に新天地を求め、守旧勢力を駆逐し、覇権を打ち立てた北条早雲。その国家像と為政者像を注目の作家が描く歴史巨編。
半ば死に体の幕府内の争いから抜け出し、東国の関東管領、関東公方などの室町時代からの秩序を壊して、新たな世を再構築しようとする早雲。
経世済民の先駆けとならんとする早雲の在り様が見事。